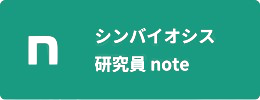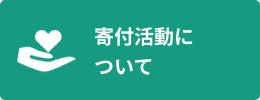私たちJapanbiome®︎(ジャパンバイオーム)は、糞便微生物叢移植のためのドナーバンクです。
所属するドナーは、厳しい検査基準をパスし、自分の元気な腸内細菌たちを病気の方のために役だてたいという思いで便の提供を行うボランティアたちで構成されています。
【糞便微生物叢移植って?】
私たちのお腹には100兆以上の個性豊かな腸内細菌たちが棲み着き、私たちが健康に暮らしていくお手伝いをしてくれています。免疫力、自律神経の調整、食べ物の代謝、組織の再生、全身の臓器との通信など、彼らの役割は多岐にわたります。
そんな腸内細菌の生態系を、「腸内細菌叢(そう)」または「腸内フローラ」と呼びます。
腸内細菌たちは、私たちの心身の状態に合わせて日々少しずつ存在比率や働きの強さ(バランス)を変えながら、私たちの体のダメージを最小限にとどめてくれています。
けれど、食の欧米化や抗生物質の多用、行き過ぎた清潔主義、ストレスの多い生活などにより、現代人の多くは、多かれ少なかれ腸内フローラが乱れています。遺伝子解析技術の進歩により、腸内フローラの乱れが様々な疾患に関わっていることが明らかになってきました。
【腸内細菌との関連が指摘される疾患一覧】
・潰瘍性大腸炎
・クローン病
・過敏性腸症候群
・うつ病
・自閉スペクトラム症
・便秘症
・糖尿病(Ⅱ型)
・脂質異常症
・がん
・アトピー・アレルギー
・婦人科系の疾患(月経困難症、不妊、更年期障害など)
・腎臓病
・心疾患
・パーキンソン病
・その他の自己免疫疾患など
上記以外にも様々な疾患との関連が報告されています。
彼らの世代交代のスピードは、早いものでなんと20分。まだまだ元気に働ける腸内細菌たちでも、便(うんち)として体の外に出ていってしまいます。そこで、健康なドナーの便に含まれる腸内細菌を不調や病気に苦しむ患者様の腸に注入することで、まるで応援団や頼りになる先輩社員のように、乱れた腸内細菌を整えることのできる有効な方法として注目されているのが「糞便微生物叢移植」です。
Japanbiome®︎の理念
私たちは、以下の理念を掲げ、安全で効果的な糞便微生物叢移植の開発・普及に努めます。
①安全なドナー便の確保・共有により糞便微生物叢移植をより身近に
②選択すべきドナー特性の検証
① 安全なドナー便の確保・共有により糞便微生物叢移植をより身近に
日本国内の糞便微生物叢移植において、多くの場合は心理的な配慮から二親等以内のドナーを自分で見つけることが条件となっています。
遺伝子学的・生活習慣的に類似した二親等以内のドナーを使用することに科学的な根拠は示されておらず、むしろ全く類似点のない第三者ドナーの方が好ましいという報告も相次いでいます。
さらに、二親等以内に健康なドナーが見つからない場合や、患者さんの腸内環境の状態や臨床症状等に応じて適切なドナーを外部から選択する必要が生じた場合、感染症等のリスクを排除した安全な第三者ドナーを見つけることが課題となっています。
また、個別の医療機関が患者さんの要望に応じてドナーを探し、安全性を確認し、現場で便を処理したうえで糞便微生物叢移植を行うことは、経済性・技術面・効率性などの側面からも現実的ではありません。
組織的なドナーバンクを整備し複数の医療機関でドナーを共有することで、より経済的かつ効率的かつ安定的に安全なドナー便を供給することが可能となります。 Japanbiome®︎は、臨床医にとっても、患者様にとっても、糞便微生物叢移植のハードルを下げることを目指します。
②選択すべきドナー特性の検証
腸内細菌、糞便微生物叢移植の分野は、海外では研究が進んでいるとはいえ、腸内細菌叢の構成は民族によって異なります。このことから、海外での研究成果をそのまま日本に持ち込むことはできないと考えられています。
また、様々な疾患に対応するためには、様々な背景や腸内細菌叢を持ったドナー組織が必要となります。
なぜなら、腸内細菌叢の多様性の乏しさだけではなく、生物学的分類の階級(門、鋼、目、科、属、種など)ごとの構成比の歪みなどが疾患につながっている場合、その構成比を改善するための腸内細菌叢を有するドナーでなければ、いくら多様性があっても劇的な改善には結びつきにくいと考えられるからです。
このとき、腸内細菌叢の構成比以外のドナーの特性(年齢、性別、体質、生活習慣など)も考慮に入れなければならないでしょう。
この「ドナー選択の難しさ」が、国外においてもCDI(クロストリジウム・ディフィシル感染症)以外の疾患で糞便微生物叢移植が普及しにくい理由であると思われます。
Japanbiome®︎では、ドナーの属性や血液・便検査に加えて、臨床医からリアルタイムに共有される患者さんの状態を個別に、また統計学的に分析することで、「健康な」という以上の特徴を持つ、患者様・症状ごとに理想的なドナーの選定を容易にすることを目指しています。
日本国内と海外の便バンク比較
アメリカ最大の便バンク「OpenBiome」では、対象疾患をCDIに限り国内の医療機関に安全なドナー便を提供しており、当該ウェブサイトによるとこれまで43,000件以上に及ぶ便の提供を行っています。 日本国内では、2013年に大学病院を含む8施設で臨床治験の第一相が開始されたものの、未だ目覚ましい成果には結びついていないのが現状です。
糞便微生物叢移植における法整備
日本国内において、糞便微生物叢移植に関する法整備はほとんど手付かずといっても良い段階です。
厚生労働省の公式な見解によると、2018年4月1日に施行された臨床研究法にも現時点では糞便微生物叢移植は該当しません。
しかしながら、欧米ではすでに政府による糞便微生物叢移植に関する指針が発表されるなど、日本での法整備も今後進んでいくことが予測されます。
Japanbiome®︎では、近い将来糞便微生物叢移植が臨床研究法の対象になることを視野に入れながら、海外の指針を参考に運営を行っています。
[参考]
※FMT国内指針運営委員会(アメリカ国立衛生研究所、アメリカ消化器病学会)
European consensus conference on faecal microbiota transplantation in clinical practice | Gut
※欧州10カ国以上、28人の有識者会議で合意を得たFMTの臨床応用指針
倫理委員会
Japanbiome®︎は、一般財団法人腸内フローラ移植臨床研究会の倫理委員会の指導を受け、運営を行っています。倫理委員会は、下記の課題について当ドナーバンクの運営が倫理的に問題のないものかどうかを検証します。
- ドナー登録時、更新時のスクリーニング項目
- ドナーの個人情報の取り扱い
- 便の収集、保管工程における安全性の確保
- 便の加工、輸送工程における安全性の確保
- 移植現場における菌液の取り扱い指導
- その他、倫理的配慮が必要な事柄
また、定期的な意見交換会を開催し、安全性と品質の向上に努めています。
※倫理委員会承認日:2019年6月20日
ドナーの健康状態の管理
<問診票>
年齢、性別、身長、体重、抗生物質使用歴、自然分娩/母乳育児、既往歴、薬やサプリメントの使用状況、渡航歴、食習慣、睡眠習慣、等々
<医師による診察>
* 血圧、脈拍、聴診、尿検査
<血液検査>
* 血液一般検査:
白血球数(WBC)、赤血球数(RBC)、血色素量(Hb)、ヘマトクリット(HT)、MCV、MCH、MCHC、血小板数
* 生化学・免疫検査:
総蛋白(TP)、AST(GOT)、ALT(GPT)、LD(LDH)、アルカリフォスファタ-ゼ(ALP)、ChE、総ビリルビン(T-Bil)、中性脂肪(TG)、総コレステロ-ル(T-Cho)、尿素窒素(UN)、 クレアチニン、尿酸(UA)、Na(ナトリウム)、Cl(クロール)、K(カリウム)、Ca(カルシウム)、P(無機リン)、グルコース、血清鉄(Fe)、アミラーゼ(AMY)、CK(CPK)、特異的IgE、IgE (非特異的IgE)、反応性蛋白(CRP)定量、HbA1c(NGSP)、eGFR、LDL-C/HDL-C比、ASO、リウマチ因子 (RF)定量、甲状腺刺激ホルモン(TSH)IFCC、コルチゾール、アルドステロン、250HビタミンD(骨粗鬆症)、遊離トリヨードサイロニン(FT3)CLEIA、遊離サイロキシン(FT4)CLEIA
* 感染症検査:
HBs抗原(HQ)、HBc抗体、梅毒定性RPR(LA)、梅毒定性TP抗体(LA)、HTLV-Ⅰ(ATLV) 抗体、HCV抗体(第3世代)、HIV抗原・抗体、EBウイルス 抗EA IgG、サイトメガロウイルス IgM、Covid-19抗体
* 免疫機能検査:
CD4×CD8、HLADR×CD3、CD16×CD56、Cyto-3-C
* 腫瘍マーカー検査:
α-フェトプロテイン定量、SCC、CA125、癌胎児性抗原(CEA)
上記検査は下記の通り検査センターに委託しています。
* 株式会社エスアールエル
ドナー便の管理
<バランス検査>
* 16S rRNA腸内細菌叢の遺伝子解析
<便検査>
* 耐性菌検査:
MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)、VRE(バンコマイシン耐性腸球菌)、CRE(カルバペネム耐性腸内細菌科細菌)、ESBL(基質特異性拡張型βラクタマーゼ産生菌)
* 食中毒検査:
黄色ブドウ球菌、セレウス菌、ウエルシュ菌、ボツリヌス菌、赤痢菌、病原性大腸菌(EPEC,ETEC,EHEC,EIEC,EAEC)、サルモネラ菌、エルシニア菌、プレジオモナス菌、コレラ菌、腸炎ビブリオ菌、ナグビブリオ菌、エロモナス菌、キャンピロバクター菌
* 免疫学的検査:
クロストリジウム・ディフィシル抗原、ロタウイルス抗原、便中ヘリコバクター(ピロリ抗原)、結核菌(PCR)、病原性大腸菌(O抗原血清型別)、ノロウイルス抗原(EIA)、アデノウイルス抗原、真菌鏡検、真菌培養同定、一般細菌鏡検、嫌気培養同定、好気培養同定
上記検査は下記の通り、遺伝子解析企業、及び検査センターに委託しています。
* 株式会社ジー・キューブへ委託:16S rRNA
* 株式会社ビー・エム・エルへ委託:便検査項目、耐性菌、食中毒菌
外部情報提供・報告体制
Japanbiomeでは、患者さんにより安心して移植をお受けいただくために、十分な情報公開に努めています。
運営体制について
Japanbiome®︎は、一般財団法人腸内フローラ移植臨床研究会が腸内フローラ移植臨床研究株式会社に委託し、運営しています。構成メンバーや管理体制などは、当研究会のウェブサイト上などで随時公開・更新してまいります。
学術・論文情報等について
糞便微生物叢移植に関する論文、腸内細菌と各疾患に関する論文等は、一般財団法人腸内フローラ移植臨床研究会と提携する本ウェブサイトにて随時追加・更新してまいります。
ドナー情報
ドナーの個人情報保護の観点から、ドナーを特定できる個人情報や、詳細な検査結果は原則として公開しておりません。ただし、当ドナーバンクの職員が必要と判断した場合、担当主治医に対してドナーが特定できない形で検査結果の共有を行う場合があります。
Japanbiome®︎運営チーム
<ドナー診察担当医>
医療法人仁善会 田中クリニック 院長 田中 善
<職員>
シンバイオシス株式会社 上席研究員 清水 真
シンバイオシス株式会社 研究員 山本千尋
腸内フローラ移植臨床研究株式会社 田中三紀子